業務棚卸シートの作り方【テンプレ付】
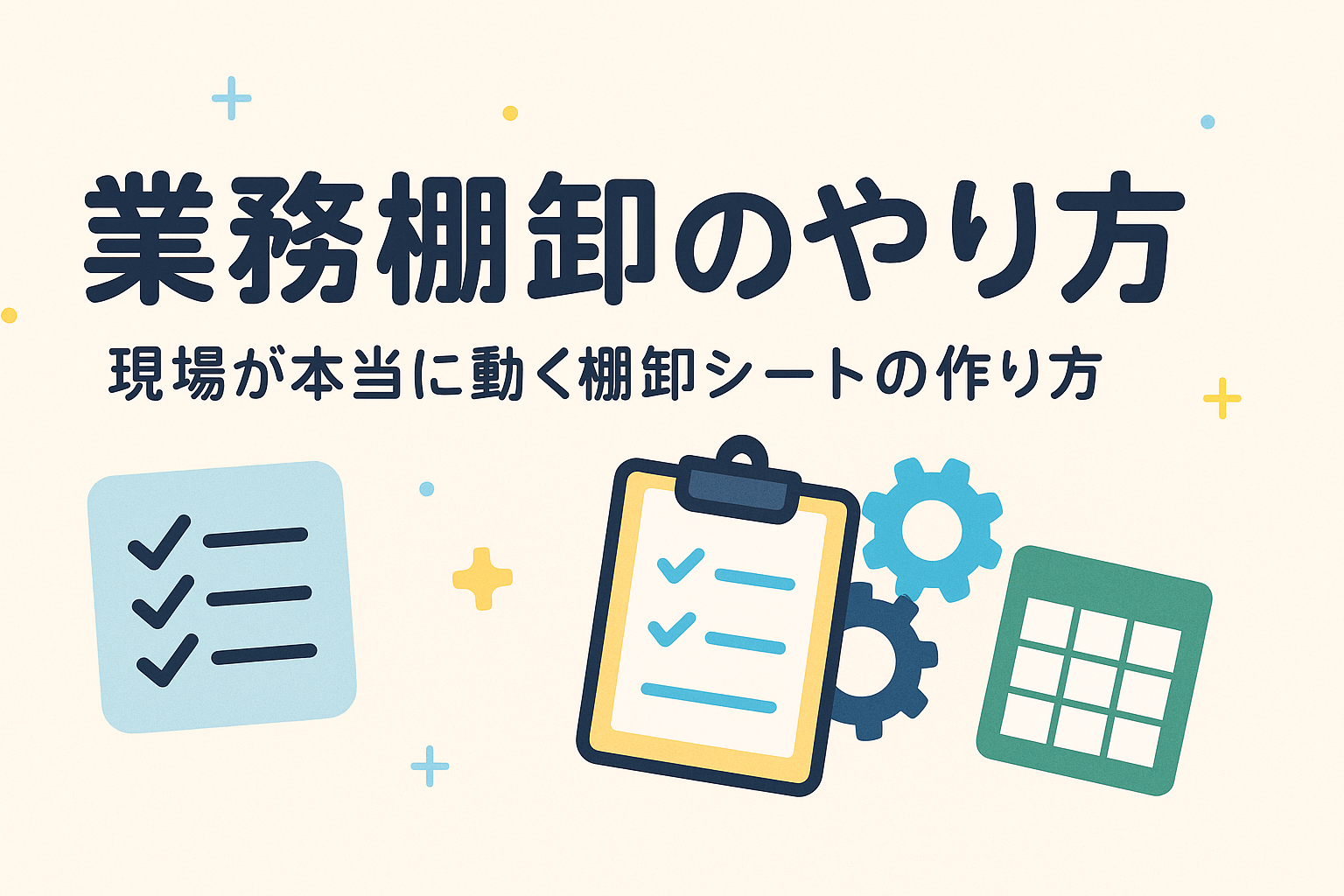
どうも、コウノ工房のコウノです。
導入システムの検討や評価をしています。
IT活用が企業の生産性を高めるのは、その通りだと思いますが、どんな業務にITを導入すればよいのかを判断するのはなかなか難しいです。そこで、今回はIT導入の判断に役立つ業務の棚卸について記事にしてみました。IT導入だけでなく、業務の引継ぎにも役立つので業務の棚卸は定期的に実行したほうがいいと思っております。
業務の棚卸とは、部署や担当者が日々行っている作業を同じ粒度で洗い出し、1枚のシートに集約する取り組みです。ここで大事なのは「仕事の名称を並べること」ではなく、“作業として実際に手を動かす単位”まで降りて書くことです。例えば「請求書処理」ではなく、「請求書PDFをダウンロード」、「台帳に金額を転記」、「上長に承認依頼を送る」というように10〜60分で完結する行動に分けて、1行ずつ記録するのがコツになります。
棚卸の目的は、単なる“見える化”ではありません。優先順位をつけ、すぐに動ける状態にすることです。現場で発生しているムダ(転記・待ち・二重入力・不要承認など)や、個人に依存している領域、ミスの温床になっている工程をあぶり出す土台にします。だからこそ、初回から完璧な台帳を目指す必要はありません。軽く始めて、回しながら育てるのがミソです。
また、棚卸は“現場への丸投げ”でも“管理側だけの机上作業”でも成果が出ません。見本行をいくつか主催側が用意し、現場の言葉で追加してもらい、週1回10分ほどの短い見直しで更新を続ける。これだけで、いつの間にか“止まらない棚卸シート”に育ち、改善や自動化の話が自然と進むようになります。
どんな企業でも、担当者の頭の中にだけある暗黙知や、過去の経緯で残った非効率なやり方があるものです。棚卸を行うと、まず全体像の穴が見えます。例えば「毎月末に時間が溶ける理由は、請求と支払に同じ情報を二重で入力しているからだった」、「入社手続きの遅れは、紙の回覧待ちがボトルネックになっていた」など、遅延の正体が具体的に掴めます。
次に、引き継ぎの強化につながります。担当者が突然休む、異動する、退職する——そんなときでも、棚卸シートがあれば最低限の運用が止まりません。新人や兼務者でも、シートを上からなぞればどこから着手すべきかが分かります。
そして、棚卸は自動化・標準化の入口です。システム化に向くタスク(規則性が高く、例外が少なく、画面操作や転記が多い作業)が一覧から瞬時に判別できます。いきなりツール選定から入るより、棚卸→要件定義→小さな実験(PoC)の順で進める方が投資対効果が読みやすく、失敗も小さく抑えられます。
では、どんなことをまとめるとよいのでしょうか?初回は列を増やしすぎず、7〜15列程度で始めるとよいでしょう。以下は、書きやすさを重視しつつ、実行に直結する推奨項目です。
- タスク名
実際の手の動きが分かるように動詞で記載(例:請求書PDFを保存/台帳に金額を転記)。 - 頻度(日/週/月/年/随時)
発生サイクル。目安:日=営業日ベース/随時=月0.5回相当の仮置きで可。 - 所要時間(分)
1回あたりの標準作業時間。15分・30分・45分・60分から選ぶ。 - 実務担当者
実際に手を動かす人。 - 個人依存度(高/中/低)
その人にしかできない度合い- 高:手順が頭の中にしかない/特定者しか対応不能(引継ぎ資料なし、属人マクロ等)。
- 中:手順はあるが解釈が必要/慣れに左右される(新人は要トレーニング)。
- 低:手順・テンプレが整備済みで誰でも実施可(新人でも当日から実行可)。
- ムダ要因(転記/待ち/承認/検索/手戻り)
時間を食う主な要因- 転記:AからBへ同じ情報を人手で再入力(二重入力・フォーマット違い含む)。
- 待ち:承認者や資料到着待ちなど手が止まる状態(システム処理待ち含む)。
- 承認:押印・合意・決裁など承認行為自体がボトルネック。
- 検索:品番・顧客名・メール等の探す作業に時間がかかる。
- 手戻り:差し戻し・不備対応で同じ作業を繰り返す(入力ミス・規程不一致など)。
- オーナー(指示者)
仕様や妥協点を最終決定できる人(役職推奨)。 - 難易度(1–5)
実装・運用変更の大変さ。- 1:マニュアルなしでも皆が同じやり方で回せる(最も易しい)
- 2:マニュアルが整備済みで、見ながら遂行できる
- 3:マニュアルはあるが、上司・識者の確認が必要
- 4:状況判断が必要(ケースバイケースで手順が変わる)
- 5:道具や仕組みの改修が必要(最も難しい)
- インパクト(1–5) ←自動算出
時間削減・品質向上・リスク低減の効き目
時間効果(基準):月間削減見込み時間により決定- 1:< 1時間/月
- 2:1〜3時間/月
- 3:3〜10時間/月
- 4:10〜30時間/月
- 5:≥ 30時間/月
加点ルール(最大+1まで):
- 個人依存度=高 → +1(継続運用のリスク大)
- ムダ要因に転記または手戻りを含む → +1(品質・再発防止効果)
- 優先度(= インパクト × (6 − 難易度))
数字が大きいほど先にやる。 - 次アクション
「誰が・何を・いつまでに」を1文で(例:経理:請求テンプレ統一案を作成 10/15)。 - 備考
例外条件・注意点・判断材料(例:紙提出が一部残存/税区分ゆらぎ など)。
最後に、棚卸は経営の意思決定スピードも上げます。改善のインパクト(コスト削減・売上寄与・リスク低減)と実装難易度を並べて評価すれば、“今月やる3件”が即決できます。資料づくりで終わらず、明日の動きが決まる——これが棚卸の価値の核心です。

